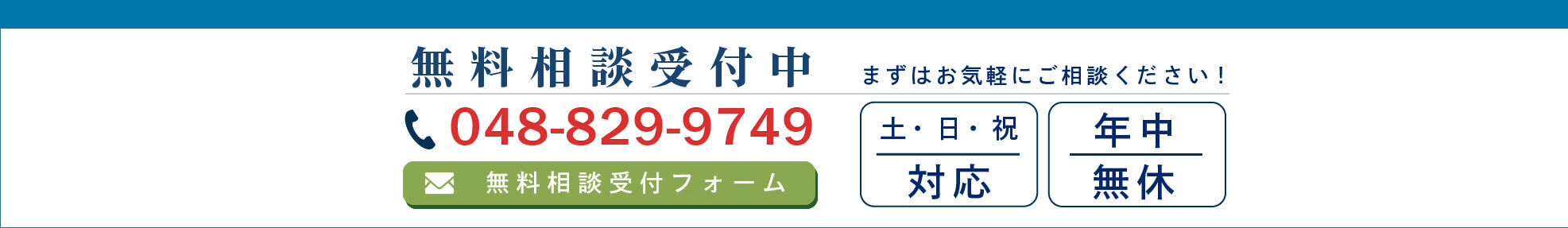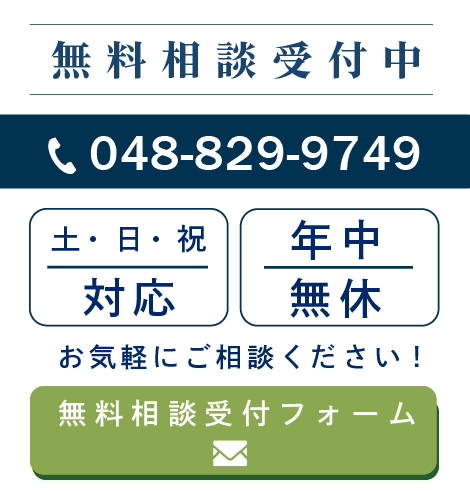アメリカの特許制度は、少し前まで先願主義ではなくて先発明主義であったり、RCEのような非常に独特な制度が多いことで知られています。
そこで、本ページでは、複雑なアメリカの特許制度を使いこなすために必要な情報をまとめたいと思います。
なお、中国への特許出願については、下記の記事をご参照ください。
【2018年度完全版】アメリカ特許出願ガイド
なぜ外国で特許を取るのか
特許権というものは、国ごとに別々に存在している権利になります。
すなわち、特許権の効力は、この特許権を取得した国の中でしか発揮できません。
これは、「特許独立の原則」と言われています。
つまり、日本で取得した特許は日本だけで有効なので、日本以外の国では真似し放題ということになってしまいます。
世界のすべての国で特許の保護を受けるには、バラバラに特許出願をして、審査を受けて特許を取得しなければなりません。
日本が承認している外国は約200か国あるので、全世界で特許を取ろうとしたらそれらすべての国の特許庁に対して特許出願をしなければなりません。
出願はその国の公用語でしなければならないので、200ヶ国向けの出願書類の翻訳を用意しなければならないことになり、
費用も膨大なものとなってしまい、あまりにも非現実的であり、予算がいくらあっても足りません。
なので、必然的に全部ではなく、いくつかの国に絞って特許を取得しておくということになっていくと思います。
どの国で特許を取得するか
では、200か国もある国のうち、どの国で特許を取得すればいいのでしょうか?
おおよその目安としては、その製品を販売する国と製造する国で特許を取得しておくべきかと思います。
製品の販売国だけでなく、製造国でまで特許を取得しておくことが重要になります。
製造を委託している工場から情報が漏れて、模倣品がすぐ近くで製造されてしまうということは、よくあることだからです。
実際には、アメリカ、中国、ヨーロッパ、日本、韓国、台湾あたりでの特許を取得することが多いです。
特に、アメリカや中国は経済規模が大きいため、重要視することが多いです。
アメリカ特許法
アメリカは、1790年に最も近代的な特許法を制定し、その後法改正を繰り返し、
多くの判例を蓄積しながら特許法を発展させてきました。いわば特許先進国です。
特許出願においても、継続審査要求(RCE)、仮出願など様々な手続きが充実していますし、
特許が成立した後にそれを潰す手続きも種類が豊富で充実しています。
また、特許を付与するシステムだけではなく、特許を行使する(侵害者を訴える)裁判所制度も充実しています。
アメリカは損害賠償の金額が大きくなることで知られているため、
現在でも多くの特許侵害訴訟が裁判所に提起され、企業同士が特許紛争を繰り広げています。
アメリカでは、特許侵害が認められた場合の、損害賠償額が非常に高額になることで知られているため、
アメリカで負けない特許ポートフォリオを築いておくことは、非常に重要です。
アメリカ(米国)に特許出願する方法
日本企業がアメリカに特許出願するには、
PCTという条約を使って、アメリカを含めた世界各国に同時に特許出願する方法(PCTルート)と、
直接アメリカに特許出願する方法(パリルート)との、2種類があります。
どちらにしても、まずは、日本の特許庁に特許出願して、
その時の出願書類を英語に翻訳して、アメリカ向けの特許出願書類とすることが通常です。
また、どちらのルートでアメリカに特許出願するとしても、日本企業の場合には、
アメリカの特許弁護士や特許出願の代理人(patent agent)に代理人をたてることが必ず必要になります。
したがいまして、日本に特許出願する段階から、アメリカでも通用する出願書類を用意することが重要です。
アメリカに特許出願する時に、書類を大幅に書き直すことになると、時間もコストもかかってしまうからです。
なお、急いでいる場合には、日本語のままの出願書類をアメリカ特許商標庁(USPTO)に提出してしまい、
そこから2ヶ月以内に、英語翻訳した書類を提出することもできます。
アメリカ直接出願(パリルート)
これは文字通り、アメリカの特許商標庁(USPTO)に、直接に特許出願する方法です。
弁理士の間では、このような出願方法は、「パリルート」などと呼ばれています。
日本企業の場合には、通常、最初に日本で特許出願することが多いと思います。
その場合には、日本での特許出願をした日から1年以内に、パリ優先権の主張という手続きをしながら、アメリカに対して特許出願する必要があるのですが、
アメリカに直接特許出願する場合には、このパリ優先権の主張を伴うことが多いことから、このように呼ばれているんだと思います。
この場合には、日本での特許出願書類を英語に翻訳して、アメリカの特許法に合わせて少しだけ修正するれば大丈夫ですので、
時間、手間、コストが比較的少なくてすみます。
PCT出願(PCTルート)
アメリカへの直接出願に対して、PCT(特許協力条約)という条約の規定を使って、世界のほとんどの国に同時に特許出願する手続きがPCT出願になります。
一旦、国際事務局という世界の特許庁のようなところに、PCT加盟国全体に対して特許出願をしておいて、その後、PCT出願の日から30ヶ月または31ヶ月以内に、
どの国に本当に特許出願をするのかを決めて、「国内移行」という手続きを行います。
現在では、パリルートよりも、PCTルートを利用して外国特許出願する方法が主流になっています。
PCTを使って外国に特許出願することは、「PCTルート」などと業界には呼ばれています。
ただ、PCTルートの場合であってもパリ優先権の主張を同時に行う場合が多く、
その場合、日本での特許出願から1年以内にPCT出願をする必要があるという点には注意が必要です。
PCT(特許協力条約)の加盟国は、2018年11月現在でも150ヶ国を超えていますので、
ほとんどの外国で特許を取りたい場合には、PCT出願でこと足りると思います。
PCT未加盟の主要な国は、台湾とアルゼンチンになります。
このように、1度の手続きで、多くの国に特許出願できるのが、PCT出願の大きなメリットです。
パリルートとPCTルートとの比較
パリルートにするか、PCTルートにするかを選択する主な基準は、
- 出願する国が何ヶ国あるのか、
- 特許化を急いでいるのかそれともゆっくりしたいのか、
の2点になると思います。
PCT出願は、各国に国内移行する前に、いろいろと審査や手続きがありますので、その分のイニシャルで費用がかかってきます。
逆に、PCT出願の場合、それ以外の費用は多数の国ににまとめてできる分、パリルートよりも安くなってきます。
目安としては、1~2ヶ国の外国(例えば、アメリカと中国など)に特許出願する場合には、パリルートにしておき、
5ヶ国以上の外国(例えば、アメリカと中国に加えて、ヨーロッパで3ヶ国など)に特許出願する場合には、PCTルートにしておくような場合が多いように思います。
他にも、特許化を急いでいるのかどうかという点も考慮する必要がります。
PCT出願は、各国に国内移行する前に、いろいろと審査や手続きがありますので、パリルートと比較すると審査の開始が遅くなります。
これは、急いでいる企業様にとってはデメリットですが、製品の事業化を見極めをギリギリまで遅らせたい
と考えている企業様にとっては、逆にメリットになります。
アメリカに対して特許出願する場合には、以上のようなことを考慮して、PCTルートとパリルートの選択をする必要があります。
アメリカ特許出願は、誰に依頼すればいいの?
結論から言えば、日本企業がアメリカへ特許出願するためには、アメリカの代理人をたてることが必須になります。
その結果、日本企業が日本の弁理士にアメリカへの特許出願を依頼し、その日本弁理士からアメリカの代理人に依頼してアメリカ特許商標庁(USPTO)に特許出願することが多くなります。
なお、アメリカの代理人とは、Patent Agent または Patent Attorney という日本の弁理士に相当するアメリカの資格を持っている人です。
アメリカの代理人に知っている方がいれば、直接頼んでアメリカに特許出願することができます。
しかし、一般的には、日本で特許出願した時に依頼した日本の弁理士からの紹介で、
アメリカの代理人に依頼するになると思います。
日本で特許出願したら、その出願書類を英語に翻訳してアメリカ特許庁(USPTO)に提出するのですが、
日本の弁理士や特許事務所で英語の翻訳までやってしまうことが多いため、
日本の弁理士と連携が取れているアメリカの代理人をたてた方が、なにかと便利だったりもします。
そのため、日本の弁理士にアメリカへの特許出願まで含めて依頼するのが、通常の方法になります。
日本の弁理士の役割
日本語は世界の言語の中で少数派の言語です。
文法も複雑で、2000字あまりの常用漢字に加え、ひらがな・カタカナを使用しています。
アメリカ人で、日本語を理解できる人は非常に少ないと考えて良いと思います。
一方、英語は世界の共通語とも言えるような状況ですので、日本人でも、多くの人が理解できると思います。
したがって、日本企業がアメリカの代理人に特許出願を依頼する場合、言語としては英語が中心となります。
そこで、日本の弁理士は、出願人(依頼人)の話を日本の弁理士が聞いて、英語でアメリカの代理人に指示を出します。
アメリカの代理人は、英語で指示を受けると、その指示に従って米国特許商標庁に手続を行います。
もちろん、日本の弁理士を介在させず、ご自身で英語でアメリカの代理人に直接指示を出して手続きを進めることもできます。
もしくは、まれに日系人が所属するアメリカの特許事務所もあるので、そういうところを探すのもよいと思います。
特許翻訳者の役割
日本の特許事務所は、専門の特許翻訳者が常駐したり、あるいはその部署と連携していたりします。
また、弁理士が特許翻訳者を兼ねている場合もあります。
日本語から英語に翻訳する特許翻訳は、英語から日本語より翻訳するよりも高度な英語力とアメリカ特許法の知識が必要になります。
アメリカでいい権利を取れるかどうかは、特許翻訳者のスキルに大いに依存しています。
できあがった英語の特許明細書は、日本の弁理士が主に法的観点から内容をチェックします。
このチェックでは、単純に翻訳がうまくできているかというチェックも行いますし、
アメリカ特許法に合わせるために、英語の特許明細書が、日本語の特許明細書とは異なるように修正を加える場合もあります。
アメリカの代理人の役割
アメリカの代理人は、日本の弁理士から受け取った書類をチェックし、米国特許商標庁に提出します。
また、米国特許商標庁から通知が来たら、それを日本の弁理士に送ってきます。
アメリカの代理人と日本の弁理士のやりとりは、英語で行うことが多いです。
また、日本語ができる弁理士がいたとしても、アメリカ人のパートナーが内容を理解できるように英語にする場合もあります。
アメリカ特許出願に必要な書類
願書
こちらは、A4一枚程度の書類で、企業様の住所や会社名、発明者名などの書誌的な事項を記載した書類です。
日本での特許出願の願書と、記載事項はかなり近いです。
アメリカの代理人に必要な情報を連絡すれば、作成してもらえるます。
特許請求の範囲(クレーム)
こちらも、日本での特許出願の特許請求の範囲と基本的には同じです。
基本的には、日本での特許出願の特許請求の範囲を英語に翻訳することになりますが、
アメリカならではの注意点もいくつかあります。
クレームの記載形式
日本の特許出願では、「Cを備えるBを有するAを含む装置」といった流し書きや書き下しと呼ばれる記載方法が一般に用いられています。
しかしながら、米国では、一般的には、「Aを含む装置であって、AはBを有し、BはCを備える」といった記載方法が用いられています。
米国流のクレームの方が、語句同士の修飾関係がわかりやすく、翻訳しやすいため、あらかじめ米国型の記載方法でクレームを作成した方が良いです。
クレーム数
アメリカでは、全体のクレームの数が20個までで、かつ独立クレームが3個までであれば、庁手数料が同一料金になります。
逆に、これらの上限を超えた場合の追加手数料は非常に高額になるため、米国に出願する可能性がある場合には、当初からクレーム数に気をつけておいた方が良いです。
マルチ従属クレーム
アメリカでは、多数の項に従属するクレームは、その親となる項数に応じて、クレーム数がカウントされることが知られています。
つまり、いわゆるマルチ従属するクレームを用いると、20個のクレーム数の上限に簡単に達してしまい、追加手数料発生の原因になりやすいです。
したがって、米国に出願する場合には、国内移行時にマルチ従属クレームをシングル従属クレームに補正しておくことが一般的です。
これを知らないで手続を進めていたとしても、おそらく現地代理人が気付いて、補正しておいてくれると思います。
また、マルチ従属項にマルチ従属項がくっつくいわゆるマルチのマルチは米国では拒絶理由になっていますので、この場合も、シングル従属になるように補正しなければなりません。
明細書
こちらも、日本での特許出願の明細書と基本的には同じです。
基本的には、日本での特許出願の明細書を英語に翻訳することになります。
したがって、日本での特許出願のときから、外国語に翻訳しやすいような文章にしておくことが重要です。
具体的には、
- 主語と述語を明確にする
- 短文にする
- 簡潔な表現を使う
- 同一の意味を表す場合には、同一の語を使う
ことが重要です。
これらを意識した明細書を普段から書くと、日本での特許出願の明細書もわかりやすくて良いものになると思います。
図面と要約書
こちらも、日本での特許出願で使った書類を英語に翻訳すれば十分です。
英訳の際の注意点
明細書を日本語から英語に翻訳する場合、基本的には直訳にします。
日本語を直訳すると、英語表現としては不自然だったり、回りくどくなったりすることがあるため、そのような場合には多少意訳することもあります。
ただし、本来の技術的意味が欠落してしまったは意味がありませんので、たとえ英語表現として多少不自然であったとしても、
意味がきちんと読み取れ、論理的に理解できるのであれば、あえてあまり修正せずに直訳するという選択肢もあります。
内容を追加することができる
英訳はほぼ忠実な直訳がよいと書きましたが、内容を追加することもできます。
例えば改良発明があったときにその改良発明を追加した明細書を作って、提出することもできます。
改良発明を追加する場合であっても、元の明細書に書いてあった内容は漏れなく英語の明細書に含ませておいたほうが無難です。
それは審査を受けた時に、明細書の内容に基づいてクレームを補正したりして特許を受けることができるようになります。
「書いてあったはずのものが書いてない」となると、いい権利が取れなくなる恐れがあります。
この場合、優先権の主張は元の日本語の明細書に書いてあった発明だけについて有効となります。
後から追加した改良発明については優先権の効果は発生しません。
優先権が発生する、発生しない、とは、新規性・進歩性の判断は優先権が効く発明については優先日を基準に判断し、
優先権が発生しない発明については実際の出願日を基準に判断するという意味です。
prior art(従来技術)という用語は使わない
英語でprior art(従来技術)というときは、それはすでに公知になっている技術という意味で扱われます。
したがって、明細書の中でうかつにprior artという用語を使ってしまうと、出願人がその技術が公知であることを自認したものとして扱われます。
そして、それを理由に新規性や非自明性を否定される可能性があります。
なので、従来技術を記載するときは、できればbackground art(背景技術)や conventional art(慣用技術)という呼び名を使いましょう。
背景技術の説明は簡潔にする
日本の明細書は、冒頭は背景技術の説明から入り、続いて、背景技術の課題を書き、そしてそれに対する解決手段を提示するというストーリになっています。
これは、日本や欧州では、課題ー解決アプローチという手法が主流なため、例えば、課題を強調したいがために、背景技術を細かく説明しているような場合も珍しくありません。
しかし、アメリカでは、課題ー解決アプローチをとらず、発明の構成を淡々と説明するスタイルをとる傾向があります。
背景技術は簡潔なほうがよく、背景技術の説明はせいぜい1ページ程度に収めるようにしたほうがよく、わざわざ図面を用いて説明することもしません。
課題は広く書く
日本や欧州における課題ー解決アプローチでは、解決すべき課題に対する解決手段という流れがとてもとても重要です。
しかしアメリカでは課題ー解決アプローチを採用していないので、課題を大げさに強調する必要はありません。
むしろ、アメリカではその発明が予測可能であるかどうかという予測可能アプローチをしますので、
例えば、従来からこういう問題の解決が期待されていた、などと演出すると、非自明性がないとされていれてしまうおそれがあります。
つまり、設計変更へのインセンティブや市場の要望などを強調すると、その発明は「予測可能」だったといわれかねないので、
課題は広めに、具体的には発明の非自明性を考えて狭すぎず広すぎず、バランスのよい課題を記載しましょう。
アメリカ特許出願に必要なサイン書類
アメリカで特許出願するには、日本などの通常の国の特許出願書類とは別に、
宣誓書(Declaration)、譲渡証(Assignment)、委任状 (Power of Attorney)という
サイン書類が3つ必要であるという特徴があります。
これらの書類は、それぞれの提出期限までに提出すれは問題ないのですが、
慣例的には、アメリカに特許出願するのと同時に全部まとめて提出してしまうことが多いです。
まとめて提出してしまった方が、出し忘れを防げますし、
アメリカの弁理士に支払う手数料も安く済む場合があります。
宣言書 (Declaration)
宣誓書とは、発明者が誰であるかということを宣誓して証明する役割を持つ書類です。
したがいまして、サインをするのは、発明者です。
サインする人: 発明者
提出期限: 登録料納付まで
譲渡証 (Assignment)
譲渡証とは、特許を受ける権利を、発明者が所属企業に譲渡したことを証明する役割を持つ書類です。
サインする人: 発明者
提出期限: 特になし
*係属中に出願の承継があった場合は、委任状の提出の時に発明者から原出願人までのChain of Title(譲渡履歴)の譲渡証を、すべて提出する必要があります。
委任状 (Power of Attorney)
委任状とは、弁理士を代理人として委任したことを証明する役割を持つ書類です。
サインする人: 出願人
提出期限: 特になし
*委任状がないとできない手続きがあるため、なるべく早めに提出することが望ましいです。
アメリカの特許要件
ここまで紹介したことを抑えてもらえれば、とりあえずアメリカに特許出願するところまでは進められると思います。
しかし、その特許出願が、実際にアメリカで特許として認められるかどうかは、ここに書く特許要件を満たすかどうかにかかってきます。
新規性(102条)
2011年の法改正により、アメリカでは、昔の先発明主義(first-invent system)から、新しい先発明者先願主義(first-inventor-to-file system)へと変更になりました。
アメリカ特許法の新規性の条文は、以下になります。
| 102条.特許要件;新規性 (a)新規性;先行技術一人は、以下の場合を除き、特許を受けられる。 (1)そのクレーム発明が、そのクレーム発明の有効出願日前に、特許され、印刷刊行物に記載され、公に使用され、販売され、又はその他公衆に入手可能であったとき;又は (2)そのクレーム発明が、151条によって発行された特許、又は122条(b)によって公開され又は公開された物とみなされた出願に記載され、その特許又は出願が他の発明者を記名しており、かつそのクレーム発明の有効出願日前に有効に出願されていたとき 35 U.S.C.102 Conditions for patentability;novelty. (a) NOVELTY;PRIOR ART.-A person shall be entitled to a patent unless- (1) the claimed invention was patented,described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b),in which the patent or application , as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention. |
アメリカ特許法102条(a)(1)は、日本の特許法の29条1項各号の新規性と、39条の先願主義の要件を両方合わせたような規程になります。
新規性の解釈において、日本とアメリカでは実質的にほぼ同じと考えて良いと思います。
つまり、特許出願に関する技術的なアイデアが、まだ世の中に公開されていなければ、O.K.です。
一方で、アメリカのグレースピリオド(grace period=one year rule)の規程は、現在の日本と同様に1年間認められます。
自己の発明を公開しても、その日から1年以内に出願すれば、その公開された発明は、その出願の審査において先行技術とはなりません。
また、アメリカでは、日本と異なって、出願時には特段の手続きをしなくとも、グレースピリオドの適用を受けるための手続は任意的であって、事後的に規則1.130等の宣誓書を提出すればグレースピリオドの利益を受けることができます。
日本の新規性喪失の例外のアメリカのグレースピリオドの比較まとめ
| 日本 | 米国 | 相違 | |
| 行為者 | 特許を受ける権利を有する者 | 発明者。または共同発明者 | △ |
| 行為 | 発明が29条1項各号(公知、公用、刊行物記載、または電気通信回線を通じて公衆に利用可能)に該当するに至ったこと | 主題が開示されたこと | ◯ |
| グレースピリオド | 新規性を喪失した日から1年以内 | その開示が有効出願日前1年以内 | × |
| 手続 | ①その旨を記載した書面を出願と同時に提出しなければならない(30条3項)。 ②証明書面を30日以内に提出しなければならない(30条3項)。 ③30条3項の手続をしなければ例外規定の適用はない。 |
①出願時に、グレースピリオド期間内の発明者の開示に関する陳述を明細書に含ませることができる(規則1.77(b))。 ②出願後であっても、その開示が102条(b)の例外規定によって102条(a)の先行技術に該当しない旨を立証することができる(規則1.130)。 ③出願時に陳述してもよいし、審査段階で先行技術が引用されたときに、宣誓書を提出してもよい。 |
×
× |
| 効果 | 29条1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす(30条2項)。 | そのクレーム発明について(a)(1)項における先行技術とはならない(102条(b)(1))。 | ◯ |
| 他人の 行為 | ①グレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表すれば、新規性(39条1項)によりその出願は拒絶される。 ②グレースピリオド期間内に他人が出願すれば、先願主義(39条)によりその出願は拒絶される。 |
①グレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表しても、例外(102条(b)(1)(A))によりその出願は拒絶されない。 ②グレースピリオド期間内に他人が出願しても、例外(102条(b)(2)(B))によりその出願は拒絶されない。 |
×
|
非自明性(103条)
日本の特許法では、新規性をクリアしたとしても進歩性の要件が課されます。
アメリカでも同様に、新規性(novelty)をクリアしても、非自明性(unobviousness)の要件が課されます。
アメリカの非自明性は、実務的には日本の進歩性とほぼ同様の規程と考えて良いと思います。
アメリカ特許法の非自明性の条文は、以下になります。
| 103条.特許要件;非自明な主題
発明が102条に述べたように全く同一のものとして開示又は記述されていないとき、特許を求める主題と先行技術との差異が、その技術分野において通常の知識を有する者にとって、その主題が全体として発明のなされた時点において自明であった場合は、特許を受けることはできない。特許性は、発明のなされ方によって否認されてはならない。 35 U.S.C.103 Conditions for patentability;non-obvious subject matter. |
103条における「先行技術」は102条における先行技術をいうと解されます。
日本では、進歩性欠如の拒絶理由に対しては、組み合わせに阻害要因があるか、または有利な効果を主張すると思います。
アメリカでも同様で、teaching away(阻害要因)があるか、または unexpected result(予期せぬ作用効果)がある、のどちらかで非自明性を主張します。
記載要件(112条)
アメリカ特許法では、112条に記載要件が記載されています。
| 112条.特許要件;記載要件
(a)明細書は、その発明の又は最も関連性が近い分野の当業者がそれを使用し製造することが可能となるように、十分に、明瞭に、簡潔にかつ正確な用語をもって、発明並びにそれを整合字使用する態様及びプロセスを記述した記載を含み…発明者又は共同発明者が最善と信じる発明の態様を提示しなければならない。 35 U.S.C. 112 SPECIFICATION |
まとめると、112条(a)は、明細書が下記3つの事項を持っていなければならない
・実現可能要件(発明を実施できるかどうか)
・ベストモード(発明の最良の形態が書いてあるかどうか)
・発明の明確性(クレームに記載された発明が明確かどうか)
実施可能要件
実施可能要件(enablement requirement)とは、明細書を読んだ人がその発明を製造したり、使用できたりする程度に明細書が書いてあることをいいます。
明細書は発明の十分な情報を含んでいなければならず、明細書の情報に基づいて、当業者が過度の実験をしなくても、その発明を実施できることをいいます。
発明が電気や機械の分野であれば、その発明の構造や製造方法をしっかり記載しておくべきです。
化学やバイオの分野であれば、その発明の化学式、シーケンスリスト、組成、または実験データを記載しておくべきです。
ITや遊技機などの分野であれ、機能ブロック図などでその処理を表現し、明細書中で詳細に説明しておくべきです。
ベストモード
ベストモード(best mode)とは、発明者が最良と信じる発明の形をいいます。
日本などにはないアメリカ特許法の独特の要件です。
ベストモードは、出願人が完全な発明の開示をせずに、独占権を得ようとする試みを防止するためのものです。
発明者が、最良の実施例を隠すことは禁止されており、ベストモードは法律に定められている要件であるものの、実は、特許の無効理由にはなっていません。
以前はベストモードも無効理由の1つだったのですが、ベストモード要件はやや主観的な側面が強いため、要件を満たしているかどうかの判断が難しいという問題がありました。
そこで、2011年の新しい米国特許法ではベストモードは特許の無効理由から除外されています。
しかしながら、将来の判例で、ベストモードに関する判断が変わるかわからないため、従来通り、出願の時点でのベストモードは、明細書に書くようにしておいたほうが無難です。
クレームの明確性
保護を受けたい発明は、明確にクレームに書いておく必要があります。
例えばクレームが矛盾を含んでいたり、用語が不明確である場合は、クレーム全体が不明確ですし、
クレームに用いた用語の意味がその技術分野で通常使われている意味と矛盾する意味に用いた場合も、クレーム全体が不明確です。
クレームが明細書の内容と矛盾している場合、クレームが技術的な矛盾を含んでいる場合、クレームが新しい技術用語を含んでいるがその意味が不明な場合も、クレームが不明確になります。
程度を表す相対的な用語を使用すると、クレームは不明確になることがあります。
例えば、「ライダーの身長の58~75%のホイールベースを有する自転車」は不明確です。
なぜなら、ライダーの身長が人によって違うため、発明の範囲も不明確になります。
about(約)という用語を使った場合は、ケースバイケースですが、発明が不明確になる場合もあります。
例えば、その数値に近い先行技術がある場合は、どこまでが発明の範囲なのかが不明確となります。
ただし、aboutという文言を推奨するアメリカの代理人もいますので、技術分野に応じてよく相談をしてください。
similar(同様の、類似の)という用語を使うと、クレームが不明確となる場合がります。
例えば、クレームに「高圧力クリーニング装置及びその類似装置」と書いた場合、そのクレームは不明確となります。
「類似装置」が何であるか不明確であるからです。
このように、クレームが明確になるように、最新の注意を払ってクレームの用語を決めていく必要があります。
上記の例では、クレームが不明確になる例のごく一部です。
補正要件
米国においても、日本と同様に、出願当所の明細書、図面およびクレームに開示も示唆もされていない事項を追加する補正、
または出願当所の明細書の根本的な不備を補う補正は、新規事項の追加であるとして認められません。
ただし、一般的には、米国の特許実務では新規事項であるか否かの判断基準は、日本の特許法下における規準よりも緩やかであると言われることが多いです。
例えば、米国では、その発明に本来的に備わっている利点や効果は、例え明細書に記載されていない場合であっても、補正で追加できるという風に一般的に理解されています。
米国の特許弁護士の中には、優先権主張の基礎となる出願の番号を米国の明細書の記載の中に引用しておくことを強く勧める人がいます。
もし、米国の明細書に誤訳があっても、基礎となった出願に基いて補正ができる可能性が高いからという理由のようです。
拒絶理由通知
出願人は、拒絶理由通知に対して原則として、3ヶ月以内に応答しなければなりません。
しかしながら、応答期間は、手数料を支払えば、1ヶ月単位で最大3ヶ月まで延長できます。つまり、応答期間は、拒絶理由通知の発行日から最大で6ヶ月まで伸ばすことができます。
なお、応答期間の延長は、期間を過ぎてから、事後的に延長手続をすることができますので、安心です。
拒絶理由通知の応答策としては、日本と同じく、補正書の提出、意見書の提出があります。
補正書で特許出願を適切な形に修正し、意見書で特許出願の正当性を主張します。
また、インタビューといって、審査官との直接の面談や電話面談を、アメリカの代理人に頼んで行ってもらう方法もあります。
このインタビューにより、特許になる可能性を確かめたり、技術説明を詳細にすることができます。
その他の審査手続き
出願公開
アメリカでは、日本と同様に、特許出願から18ヶ月経過後に、その特許出願の内容が公開されます。
すなわち、特許出願に関する書類が、アメリカ特許商標庁(USPTO)にアップロードされてしまいます。
IDS(情報開示陳述書)
アメリカでは、特許出願人に、情報開示義務という義務が課せられます。
その義務を履行するために、情報提供を行う手続きが、情報開示陳述書(Information Disclosure Statement,IDSと一般的に称する)、つまりIDSの提出になります。
このIDSは、特許を出願したときから、特許が登録になるまでずっと課せられるもので、
これを怠ると、特許権を使うことができなくなってしまいますので、非常に重要度の高い手続きになります。
また、複数の国に同時に特許出願していると、アメリカの審査では示されなかった先行技術文献が、他国の審査官から提示される場合がけっこうあります。
そのような場合には、その都度、その先行技術文献をIDSとして提出する必要があります。
例えば、ライバル企業に、ライバル企業が出願中の発明に関連する先行技術文献を送りつけることで、そのライバル企業にIDSの義務を発生させるというようなトラップをしかけることも、ときどき行われています。
・提出する必要がある文献
1,本出願の明細書中で先行技術文献として紹介している文献
2.対応する日本出願(優先権基礎出願)や外国出願などのファミリー出願における拒絶理由通知などや、そこで引用された文献
3.PCTの国際調査報告などや、そこで引用された文献
4.同じ特許ポートフォリオ中の関連する案件(ファミリーでない)の審査において引用された文献
5.その他、特許出願とその権利化に関わる物が知った特許性に関する重要な情報
限定要求
限定要求は、特許出願に、発明の単一性が認められない場合に出されるものです。
1つの特許出願に2つ以上の別個の発明が詰め込まれていると判断されていますので、
出願人は、どれか1つの発明に絞るように選択しなければいけません。
1つの特許出願に、たくさんの発明が詰め込まれていると、審査が大変ですし、
費用負担の面で公平性を欠くと考えられているため、このような制度になっています。
限定要求は、それに応答できる期間が30日以内ととても短いため、迅速に対応する必要があります。
一方、限定要求は、書面でなく電話で答えるだけも良いので、急ぎの場合には電話で済ませることもあります。
なお、限定要求に応答する結果、選択しなかった発明について特許にしたい場合には、
特許出願を分割することで、別の特許とすることができます。
また、PCTルートで特許出願した場合は、アメリカ直接出願のパリルートの場合とくらべて
若干ですが、単一性の要件がゆるく、限定要求が出されにくいことが知られています。
アドバイザリ通知
アドバイザリ通知とは、最後の拒絶理由通知への応答によっても特許されない時に審査官により発行される通知のことです。名称も目的も異なりますが、日本で言う拒絶査定に該当すると考えてもよいと思います。
アドバイザリ通知への対応策としては、下記の3つが挙げられます。
- 継続審査請求(RCE)または継続出願
- 審判請求
- 放棄
継続審査要求(RCE)
継続審査請求とは、同一出願内で審査の継続を求める請求のことで、昔あったCPAに代わって導入された制度です。継続審査請求は、よくRCE(Request for continued examination)と呼ばれています。CPAは親出願の手続を引き継ぐものの、別個の新たな出願手続きが必要でしたが、RCEにより簡易な手続で審査の継続を求めることができるようになりました。
(1)RCEの時期
RCEができる時期は、出願の審査が終了した後で、次の何れかの早いときまでです。
・特許料の支払い前
。特許出願の放棄
。特許審判部による審決に対する連邦巡回控訴裁判所への出訴
要するに、一般的にRCEをするのは、アドバイザリ通知を受けた後です。特許料の支払い後であっても、請願により特許査定を取り下げてもらい、RCEが可能です。
つまり、日本でいうと、拒絶査定(アドバイザリ通知)を受けた後に、再度審査をやり直し(RCE)してもらえるようなイメージです。
(2)提出書類
情報開示陳述書、補正書、特許性を裏付ける新たな証拠を、RCEと同時に提出する必要があります。
万が一、アドバイザリ通知で補正が却下された旨が通知されていたら、クレームは補正前の状態にあるので、RCEと同時に再度補正する必要が生じます。
小規模団体(small entity)の割引
出願人が、小規模団体または極小団体(micro entity)であれば、USPTO費用が減額になります。
ここで、
小規模団体(small entity)とは、個人、小企業、非営利団体です。
小企業とは、関連会社も含めて、従業員が500人未満の企業です。
非営利団体とは、発明に関する権利を小規模団体以外の他社に譲渡・移転・実施許諾しておらず、そのような義務をも負わない、教育機関や非営利科学・教育機関などです。
小規模団体としての地位を主張する最も簡易な方法は、出願用の書式の中にある小規模団体のボックスにチェックを入れることで、50%の減額になります。
極小団体(micro entity)とは、小規模団体に該当し、さらに4以上の過去の特許出願において発明者として記名されておらず、平均家計所得の3倍以上の所得を受け取っておらず、平均家計所得の3倍以上の所得を受け取っている団体にライセンスまたはその他の所有権を譲渡等していないものをいい、75%の減額になります。
自社が従業員が500人未満であるとしても、関連会社を併せれば500人を超える場合は小規模団体ではなくなり、発明に関する権利を大企業に譲渡していたり、そのような予定があるときは小規模団体の優遇は受けられません。
アメリカ特許出願の費用
米国特許商標庁(USPTO)料金
2018年1月16日より、米国特許商標長(USPTO)の料金が値上になっております。
最新の料金を下記にを示します。
| 出願段階 | 料金 | ||||
| ・特許出願料金(基本、サーチ、審査手数料の合計) | $1,720 | ||||
| ・意匠出願料金(基本、サーチ、審査手数料の合計) | $960 | ||||
| ・仮出願料金 | $280 | ||||
| ・PCT出願の移行料金(基本、サーチ、審査手数料の合計) | $1,580 | ||||
| ・クレーム数の超過分料金(20を超える1クレーム毎) | $100 | ||||
| ・独立クレーム数の超過分料金(3を超える1独立クレーム毎) | $460 | ||||
| ・マルチ従属クレーム料金(マルチクレームが1つでもある場合、複数あっても同一料金) | $820 | ||||
| ・追完料金(出願料金、署名書類) | $160 | ||||
| 中間段階 | 料金 | ||||
| ・延長申請料金 $200/1ヶ月,$600/2ヶ月,$1,400/3ヶ月,$2,200/4ヶ月,$3,000/5ヶ月 | |||||
| ・最初のRCE申請料金(RCE:Request for Continuing Examination Fees) | $1,300 | ||||
| ・2回目以降のRCE申請料金 | $1,900 | ||||
| ・審判請求の料金(審判請求時に$800を支払い、実態審理の開始時に更に$2,240を支払う) | $3,040 | ||||
| 登録段階 | 料金 | ||||
| ・特許登録料金(公開と発行手数料の合計) | $1,300 | ||||
| ・意匠登録料金(公開と発行手数料の合計) | $1,000 | ||||
アメリカ(US)での特許権の効力
アメリカでは、日本と比べて、訴訟における損害賠償の金額が非常に高いことが知られています。
これは、特許侵害訴訟においても例外ではないことから、アメリカでは、自社の特許ポートフォリオを充実させて、
特許権侵害訴訟から身を守ることが非常に重要になってきます。
また、特許侵害訴訟が頻繁に行われることから、その対抗手段として、相手の特許を潰す手続きが重要になってきます。
相手の特許を無効にしたい
アメリカの特許法では、現在、特許を潰すための手続きが4つあります。
- 査定系再審査
- 付与後レビュー
- 当事者系レビュー
- ビジネス方法レビュー
無効審判と異議申立ての2つしかない日本と比べて多彩で、非常にアメリカらしいと思います。
これだけあると、それぞれの状況に応じて使い分けることができます。
ただ、数が多すぎてちょっとわかりにくいかもしれません。
この4つの1つ1つを、以下に詳細に説明いたします。
査定系再審査
概要
再審査(reexamination)とは、特許の発行された後、特許庁が先行技術に基づいてクレームが特許性を有するか否かを審査することをいいます。
旧法では、再審査は、査定系再審査(ex parte reexamination) と、当事者系再審査(inter partes reexamination)の2種類があり、
当事者系再審査が当事者系レビューとして、名称も中身もリニューアルしました。
一方、査定系再審査はそのまま残っており、特許権者が請求すれば「審査の再開」となり、第三者が請求すれば日本でいう「異議申立て」に近い手続きとなります。
活用方法
特許権者が自己の特許の有効性を確認したいとき、査定系再審査を利用します。
例えば、特許が発行された後に、新たな先行技術文献が発見されてクレームの特許性に疑いが生じたとき、
審査の過程で情報開示しなかった(または情報開示をしたが審査官に考慮してもらえなかった)先行技術があるとき、
特許権者は先行技術文献を自ら提出して再審査を受けることができます。
また、第三者が特許に異議を申し立てたいとき、再審査を利用することができます。
例えば、クレームの特許性に重要な関連性を有すると思われる先行技術を発見した時、
第三者は発見した先行技術を提出するとともに、再審査を請求することができますが、
査定系再審査は第三者が積極的に特許性を争う手段としては不十分です。
なぜなら、最初は第三者の請求でスタートしますが、請求後は弁駁の機会が与えられるものの、
その後は特許権者と審査官との間だけで審理が進行し、第三者は参加する機会が与えられないからです。
結果、特許権者と審査官との間の議論だけで手続きが進み、特許権者の有利な結論に導かれてしまうおそれがあるからです。
第三者が特許の有効性を争う手段としては、他に付与後レビューと当事者系レビューがあるので、そちらの手続きを検討すべきです。
その一方で、査定系再審査は匿名でも請求することができるので、第三者が自分の正体を知られずに、特許の有効性を争いたい場合に活用することができます。
また、査定系再審査は、付与後レビューや当事者系レビューなどの比べてUSPTO料金が安いです。
そのため、特に切迫した特許侵害の紛争がなく、やんわりと特許を攻撃したいときに有効な手段かもしれません。
付与後レビュー
概要
付与後レビュー(post-grant review)は、特許付与された後9か月以内に、第三者が申し立てて特許の有効性を争うことができる制度で、期間限定の異議申し立てということができます。
似たような制度として、日本で2015年4月から導入された異議申立て、欧州特許条約(European Patent Convention)における異議申立てがあります。
付与後レビューは、特許付与の直後の初期段階で特許を見直すことによって、
特許権のクオリティを素早く担保することを目的としています。
しかし、日本での異議申立ては審判官が特許を見直す審査的手続きであるのに対して、付与後レビューはどちらかというと裁判的手続きとなっています。
つまり、従来は特許の有効性は侵害訴訟の一連の手続きの中で裁判所において争われていましたが、
特許の有効性を技術的専門知識がない裁判官が判断するのは容易ではなく、特許の有効性を争うのにいちいち裁判所で争うのは費用も掛かるため、
特許の有効性についての裁判手続きを。技術専門家がいる米国特許商標庁で代替する手段という位置づけになります。
特徴
付与後レビューは、後述する当事者系レビューよりも審理開始の敷居が高くなっています。
付与後レビューでは、請求人が半分以上の確率で勝ち目がないと手続きが開始されないので、第三者は勝機について自信がある場合に限り利用するのがよいと思います。
付与後レビューと当事者系レビューを二重に係属させることはできないので、第三者は付与後レビューか当事者系レビューのどちらか一方をせんたくしなければなりません。
また、付与後レビューはとても審理が迅速で、12か月(または、延長された場合でも最大18か月)の期間内に終了します。
さらに、訴訟的な手続きが取り入れられており、当事者はディスカバリを行うことができます。
ディスカバリとは、情報を証拠として提出することをいい、当事者が所有・管理している書類、電子的に記録された情報などを開示させる手続です。
それから、費用が高額です。当事者系レビューの費用も高額ですが、付与後レビューはさらに高額に設定されています。
例えば、クレーム数1から20までの場合だと、35,800ドルが庁料金となります。これに米国の弁理士費用も加算されるので、相当高額になると思います。
活用方法
付与後レビューの対象となる特許は、2013年3月16日以降(当日を含む)の優先日を有する特許です。あまり古い特許に対しては申立てできません。
付与後レビューは、特許の付与の後9か月よりも前に提出しなければならないので、あらかじめ相当な準備をしておかなければ利用できないでしょう。
対象となる出願をあらかじめ知っていて、特許性に影響を与える証拠を集めておいて、それが特許になったときに付与後レビューの請求をしなければないため、
日ごろから特許紛争を繰り広げていて、あるいは問題となる特許が審査にかかっていて、なんとしても特許を早くつぶしたいときに利用すべきでしょう。
当事者系レビュー
概要
当事者系レビュー(inter partes review)は、特許付与後に第三者が特許の有効性を争う代表的な手続きで、日本でいう無効審判に該当する手続です。
しかし、日本の無効審判が第三者の請求の基づき、行政庁が行政処分を取り消すための手続きであるのに対して、
当事者系レビューは連邦裁判所での訴訟手続きの代替手段という位置づけです。
要するに、代替手段とは、本欄は裁判所で行うべき手続きを米国特許商標庁で行うようにしたという意味です。
特徴
当事者系レビューは、審理開始の敷居が、付与後レビューよりは低いです。
付与後レビューは、請願人に50%以上の勝機がなければ審理が開始されませんが、当事者系レビューは請願人に50%程度の勝機があれば審理が開始されます。
また、付与後レビューは特許付与から9か月以内に請求しなければなりませんが、当事者系レビューでは期限がないので、当事者系レビューのほうがずっと使いやすい制度であるといえます。
なお、当事者系レビューは裁判所での裁判手続きの代替手段ですので、当事者系レビューを米国特許商標庁に請求したら、同じ特許の有効性を裁判所で争うことはできません。
また、付与後レビューと当事者系レビューの2つの手続きを重複してすすめることはできないのです。
また、当事者系レビューと付与後レビューを二重に請求することはできないので、どちらか一方を選択しなければなりません。
当事者系レビューの審理は迅速に行われます。審理は12か月(または、延長された場合でも最大18か月)の期間内に終了します。
さらに、付与後レビューと同様に、訴訟的な手続きが取り入れられています。当事者はディスカバリを行うことができます。
ディスカバリとは、情報を証拠として提出することをいい、当事者が所有・管理している書類、電子的に記録された情報などを開示させる手続です。
それから、費用が高額です。付与後レビューの費用が高額であることは前述したとおりですが、それよりもやや低額に設定されているとはいえ、当事者系レビューも費用は高額です。
例えば、クレーム数1から20までの場合だと、27,200ドルが庁料金となります。
これに米国の弁理士費用も加算されるので、かなり高額になってしまいます。
活用方法
当事者系レビューの対象となるのは、すべての特許です。期間の制限はなく、古い特許に対しても請求することができます。
2013年3月16日以降の優先日を有する特許だけが対象となる付与後レビューよりもずっと使いやすいと思います。
例えば、事業の妨げとなる競争相手の特許があった場合であれば、それが古い特許であっても、請求することができます。また請求の期限があるわけではないので、
事情が許せば、じっくり先行技術を集めて、無効の論理付けをしっかり作ってから請求することができます。
したがって、当事者系レビューは第三者が特許の有効性を争ううえで、最もポピュラーな手続きであるといえると思います。
ビジネス方法レビュー
概要
特許を無効にする手続として、2020年9月16日まで施行される期間限定の制度ですが、特にコンピュータ関連発明の特許を無効にする、ビジネス方法レビュー(covered business method review)という制度があります。
このような暫定的な制度が作られた理由としては、1990年代後半から2000年代前半にかけて、
質の低いビジネス方法特許が付与され、これらがパテントトロール訴訟に利用されていたという実情がありました。
パテントトロールとは、自ら事業を行わない者が特許を譲り受け、大企業を訴えて巨額の賠償金をせしめようとする団体を言います。
合法ではありますが、産業の発達を促すという特許制度の趣旨に反して、産業の発達に寄与せずに単に巨額の賠償金を狙った訴訟を起こす団体です。
ビジネス方法に関する特許出願が審査されていた当時は、米国特許商標庁ではこの分野を専門とする審査官が不足していたようです。
そこで、米国特許商標庁はこの分野の特許の審査を強化する意味合いで、
この期間限定の制度を作ったようです。
特徴
ビジネス方法レビューの対象は、ビジネス方法特許に限定されます。
ビジネス方法特許とは、例えば、金融商品の実施、管理、または運用に使用されるデータ処理に関するものをいい、特に非技術的なものに限定されます。
金融商品とは何であるかが問題となりますが、本質的に金融的であるとか、金融活動に付随するとか、
または金融活動を補完する活動全般を含む広いサービスであると解釈されています。
ビジネス方法レビューの手続きは、付与後レビューの手続きを似ていますが、付与後レビューの期限(特許の付与の日から9月)という制限はありません。
期間の制限はなく、いつでもビジネス方法レビューを請求することができます。
ただし、ビジネス方法レビューを請求するには、実際に侵害と問われていることが必要となります。
実際に侵害の警告を受けていて、そのような訴訟が提起されようとしていることが必要です。
この点、そのような切迫した状況でなくてもよい付与後レビューや当事者系レビューとは違います。
活用方法
ある特許を無効にしたいとき、当事者系レビューかビジネス方法レビューのどちらかを選択するかが問題となります。
対象となる発明がビジネス方法に関するものであり、実際に侵害と問われているという切迫した状況があるときは、ビジネス方法レベルを利用するとよいです。
そのような特別な状況ではないときは、当事者系レビューを選択するということになるかと思います。